安全・安心情報
更新日:2022年3月17日
ここから本文です。
県のプロフィール[富山県のシンボル]
覚えておきたい、富山の顔。
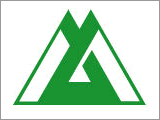 県章
県章
昭和63年(1988年)12月27日制定
富山県のシンボルでもある立山をモチーフに、その中央にとやまのイニシャル「と」を配しています。大空に向かって躍進する富山県をイメージしています。
使用については、こちらをご覧ください。
 県花 チューリップ
県花 チューリップ
昭和29年(1954年)3月22日選定
本県は、日本一の出荷量を誇るチューリップ球根産地であり、約300の品種が栽培されています。4月下旬になると、砺波地方をはじめ各地で色とりどりの花のじゅうたんが見られます。
 県鳥 ライチョウ
県鳥 ライチョウ
昭和36年(1961年)11月3日制定
日本アルプスの代表的な高山鳥であるこの鳥は、特に県民が仰ぎ親しんできた霊峰立山に多く生息し「立山神の使い」として愛されています。[特別天然記念物]
 県木 タテヤマスギ
県木 タテヤマスギ
昭和41年(1966年)10月1日制定
立山を中心とする山岳地帯に自生しています。寒さや雪に強いという特徴をもち、まっすぐに天に向かって伸びる姿は、たくましい生命力を感じさせます。
 県獣 ニホンカモシカ
県獣 ニホンカモシカ
昭和50年(1975年)10月4日制定
標高500~2,000mの森林地帯や岩場に生息し、県内では立山連峰や黒部峡谷に多く見られます。厳しい自然環境の中で黙々と生き抜く姿は、県民の姿に例えられます。[特別天然記念物]
 県のさかな ブリ
県のさかな ブリ
平成8年(1996年)10月12日制定
「ツバイソ(コズクラ)」「フクラギ」「ガンド」「ブリ」と呼び名を変える出世魚で「富山湾の王者」としての風格があります。特に「寒ブリ」は脂がのっておいしく、冬の富山湾を代表する味覚です。
 県のさかな ホタルイカ
県のさかな ホタルイカ
平成8年(1996年)10月12日制定
3月から6月にかけて産卵のために富山湾沿岸を群遊します。体に多くの発光器を持ち、暗闇で青白く光る幻想的な様は、まさに「富山湾の神秘」です。
 県のさかな シロエビ
県のさかな シロエビ
平成8年(1996年)10月12日制定
富山湾の海底谷(水深100~600m)に生息し、富山湾が日本唯一の漁場となっています。生きているものは透明な淡いピンク色で美しく「富山湾の宝石」と呼ぶにふさわしいものです。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください